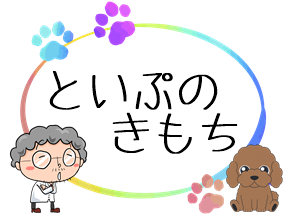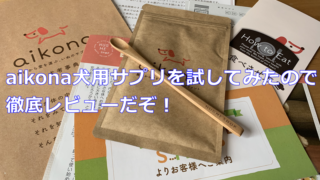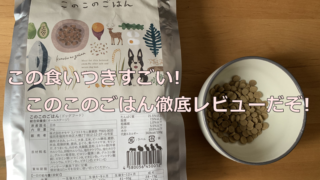といぷ博士ですぞ!
愛犬が突然しゃっくりをし始めて驚いたことはありませんかな?
実は人間と同じようにわんちゃんもしゃっくりをするのですぞ。
犬のしゃっくりは一度出るとなかなか止まらないことも多く、苦しそうにも見えるので「なにかの病気?」と心配になるかと思いますが、ほとんどの場合生理的な現象と言われているのでそこまで心配する必要はないようです。
しかし、あまりにもしゃっくりが長く続いたり頻繁に起こる場合は病気のサインということもあります。
また寝てるときにしゃっくりのようなものをする犬もいます。
これって何なのでしょうか?




今回はそんなしゃっくりの原因や対処法などをまとめてみましたよ。
トイプードルもしゃっくりをする?
トイプードルも人間と同じようにしゃっくりをします。
しゃっくりをするしくみも同じで、横隔膜が痙攣した時に起きるようになっています。




とくに子犬の頃は横隔膜が発達していないのでしゃっくりが多くなるようですが、大人になるにつれて回数は減っていくようですよ。
トイプードルがしゃっくりをする原因は?

犬がしゃっくりをする主な原因は「ごはんの食べ方」「ストレス」「病気のサイン」の3つが考えられます。
ごはんの食べ方
特にごはんを早食いしてしまう犬は、ご飯と一緒に空気も飲み込んでしまうので急激に胃が大きくなることで横隔膜を刺激し、しゃっくりが出てしまうのです。
どうしても早食いしてしまう犬であれば、早食い防止の食器に変えたり食事の量を減らして回数を増やすなど胃に負担がかからないごはんの与え方に変えてみると良いですよ。
食後すぐに運動をすることも胃にガスが発生しやすくなり、胃が膨らんでしまう原因になるので気を付けてあげましょう。
参考記事 トイプードルの早食いは大丈夫?犬が丸呑みしちゃう理由と防止法をどうぞ


ストレス
犬は環境の変化にとっても敏感です。
この環境の変化は愛犬にとってストレスと感じる事が多く、犬がストレスを感じると自律神経が乱れてしゃっくりが出る原因となることもあるのです。
ストレスが原因でしゃっくりが出ている場合は、なにか不安を感じていたり恐怖を感じている場合もあります。
愛犬がリラックス出来るようにスキンシップをしっかりとって、お散歩などでストレスを解消してあげると良いでしょう。
病気のサイン
普通しゃっくりは短時間で止まることが多いのですが、あまりにも長く続く場合や回数が多い場合は病気が隠れている可能性があります。
特に多いのが喘息や肺炎などが考えられますが、中には消化器系や循環器系などの病気が見つかることもあります。




少しでもおかしいな?と感じたら動物病院へ相談してみることをお勧めします。
トイプードルのしゃっくりが止まらないときの対処法
トイプードルのしゃっくりも人間と同じで時間がたてば止まりますが、苦しそうにしている愛犬を見てるのも心苦しいですよね。
愛犬がしゃっくりをし始めると飼い主さんはつい慌ててしまいがちですが、飼い主さんが慌ててしまうと愛犬も不安になったりパニックになってしまうこともあります。
愛犬がパニック状態になっていたり興奮している場合は、まずは落ち着かせてあげることから始めてみましょう。
しゃっくりを止めるには愛犬の呼吸のリズムを整えてあげると止まりやすいと言われています。
呼吸のリズムを整えるには、水を飲ませたり、飼い主さんの指を舐めさせることで止まる場合もあります。
また、愛犬のみぞおちあたりを優しくマッサージしてあげると横隔膜の痙攣を押さえる事ができ、しゃっくりが止まりやすくなります。




愛犬が落ち着いた様子であれば、散歩をしたり軽く運動をさせてあげるのも呼吸のリズムが変わりしゃっくりが止まりやすく、愛犬の気分転換にもなりいつの間にか止まってたということもありますぞ。
犬が寝ているときにしゃっくりをするのはなぜ?

中には寝ているときにしゃっくりのような状態になる犬もいます。
犬の睡眠は眠りの浅いレム睡眠と眠りの深いノンレム睡眠を繰り返します。人が浅い眠りの時にこそ夢を見ると言われるように犬もこのレム睡眠の時に夢を見ているとされますね。
ということは…そのしゃっくり、寝言の可能性が大です!
仮に病気であるならば、日中にも同様の症状が現れるはずですが、寝ているときだけなのであればおそらく寝言であると考えていいでしょう。
人の寝相や寝方がさまざまであるように、犬だって様々な寝方をしているはずです。
一度じっくりと愛犬が寝ている姿を観察してみるのも面白いかもしれませんよ。
参考記事 トイプードルの睡眠時間ってどれくらい?寝てばかりの犬は夢を見るの?


まとめ

愛犬の突然のしゃっくりに驚いてしまいますが、原因や対処法が分かっていれば落ち着いて対応出来そうですよね。
しゃっくりのほとんどの場合は問題ないと言われていますが、まれに病気が隠れている場合もあります。
普段の生活や行動を観察して、愛犬の変化を見逃さないようにしてあげて下さいね。




よく人間の場合のしゃっくりは「驚かせると止まる」と言われていますが、犬の場合は少し可哀そうなのでやめてあげましょう。